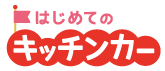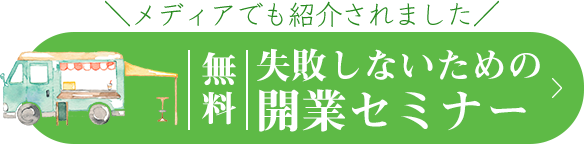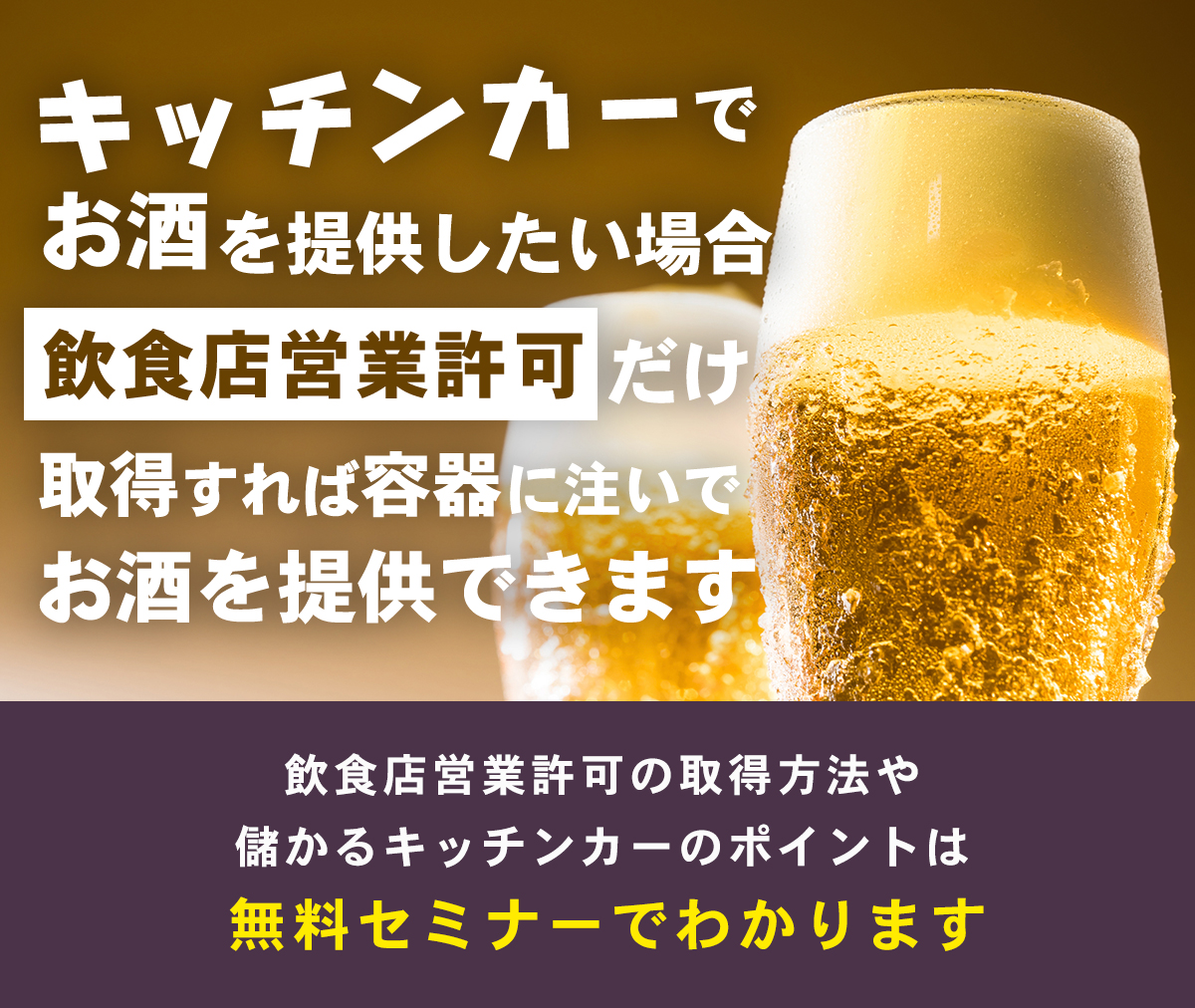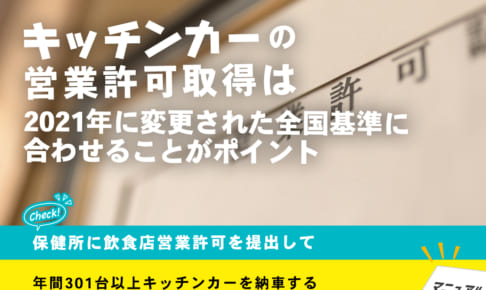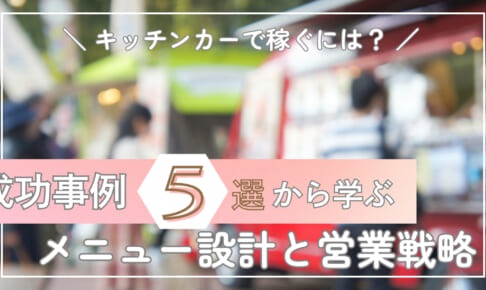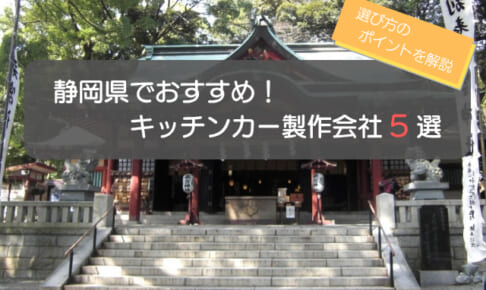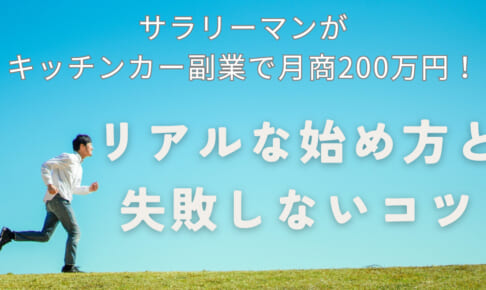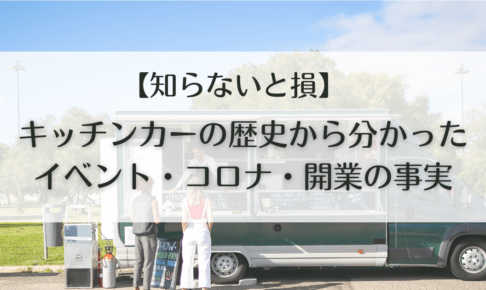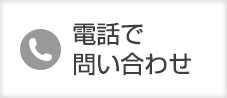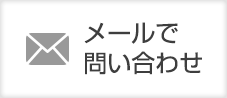「キッチンカーでお酒は販売できるのだろうか?」
「酒類の販売許可免許がないとアルコール類は扱えないんだよね?」
「イベントで生ビールを売っているお店を見るけど、どんな許可をとっているのだろう?」
こんな疑問を持っていませんか?
その気持ちはよく分かります。なぜなら、キッチンカーを開業する前は私自身が、飲食業の経験ゼロだったので、お酒・アルコール販売の知識もゼロで何も知らなかったからです。
何も知らない未経験の状態からキッチンカーを開業した経験のある私が、保健所に直接電話で確認した最新情報も交えて、キッチンカーでのお酒類の販売について情報をまとめました。
この記事では、
- キッチンカーでお酒(アルコール)を販売できる根拠
- お酒(アルコール)を販売するために守るべき条件
- 缶・瓶に入ったお酒(アルコール)は販売できない理由
- よく聞かれるキッチンカーでのお酒販売に関する疑問とその答え
をお伝えします。
キッチンカーでのお酒(アルコール)販売に関して知っておくべき情報を知識ゼロの人でも理解できるようにまとめましたので、ぜひ最後までお読みください。
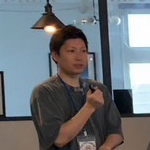 | 監修者 キッチンカー開業コンサルタント |
キッチンカー開業を志す方々の夢を形にする専門家。メニュー開発から車両選定、出店計画、開業資金の計画まで、キッチンカー開業に必要な全てをワンストップでサポートします。フードトラックカンパニーの豊富な実績とノウハウを活かし、成功への最短ルートを共に描きます。
目次
キッチンカーの営業許可でお酒(アルコール)を販売できる

キッチンカーの営業許可があれば、お酒(アルコール)を販売することが可能です。ただし、販売するお酒(アルコール)の状態によって順守すべき法律が異なるので注意が必要です。キッチンカーでお酒(アルコール)を販売するために知っておくべき基本的な知識をまとめました。
お酒の販売方法によって許可の種類が異なる
お酒・アルコール飲料を購入する際は、コンビニ・スーパー・酒屋さんなどの小売店で、缶ビールやワインボトルのように容器に入った物を購入する場合と居酒屋・レストランなどの飲食店で注文してその場で飲む場合があります。
前者の場合にはお酒を販売するために「国税庁」による「酒類販売業免許」の取得が必要です。一方、後者の場合は出店場所を管轄する保健所の「飲食店営業許可」が必要となります。
容器に注いだり開封したりすればお酒を販売できる
キッチンカーを開業するためには、保健所で飲食店の営業許可を取得しなければなりません。つまり、「飲食店営業許可」があるキッチンカーでは、居酒屋・レストランと同様にカップ・コップなどの容器に注いだ状態であればお酒を販売できます。ビールサーバーから注いだ生ビールもこちらに該当します。
一方、缶ビール・缶ハイボール・ワインボトルのように容器に入ったお酒を販売するためには、「酒類販売業免許」という「飲食店営業許可」とは全く異なる資格が必要となります。キッチンカーでは「酒類販売業免許」を取得できないので、缶ビールなどは販売できません。
厳密には缶ビールなども開封すれば缶のまま販売できますが、見映えが良くないのでカップなど他の容器に注いで販売することをおすすめします。お酒やアルコール類に限らず、キッチンカーでのドリンク販売については、下記の記事で詳しく解説しています。メニューにドリンクを入れる可能性のある人は、ぜひお読みください。
» キッチンカーの営業許可でドリンク販売が可能!タンク容量に注意!
キッチンカーでのお酒(アルコール)販売のために守るべき条件4選

キッチンカーでのお酒(アルコール)の販売は法律で認められていますが、取り扱う商品や販売方法によっては違法になる可能性があります。しっかりと法令順守でお酒(アルコール)の販売ができるよう、守るべき四つの条件を解説します。
1.飲食店の営業許可を取得する
キッチンカーを開業するためには、出店予定地域を管轄する保健所から飲食店の営業許可を取得しなければなりません。この営業許可があればキッチンカーでのお酒(アルコール)の販売は可能です。つまり、キッチンカーの営業許可さえ取得できれば、お酒(アルコール)を販売できることになります。営業許可に必要な情報は次の記事にまとめています。
» 【2024年最新版】キッチンカーの営業許可証取得を申請から4ステップで徹底解説!
2.すぐに飲める状態で販売する
飲食店営業許可で販売するアルコールと酒類販売業で販売するお酒はどちらも元は酒造メーカーが作った同じ製品ですが、どこからが飲食店営業許可でどこからが酒類販売業なのか、保健所と国税庁に「国税庁はこう言ってますが……」「保健所はこう言ってますが……」「飲める状態って具体的に何ですか?」と交互に確認した結果、違いは例えば缶ビールやワインボトルであれば「グラスに注いだかどうかではなく、缶や瓶を開栓しているかどうかで決まる」という説明になりました。
つまり、「キッチンカーは保健所で飲食店営業許可を取得することで、開栓した状態のお酒(アルコール)を販売してよい」ということになります。
3.品目数制限の法令を順守する

軽自動車をベース車両とするキッチンカーや給排水タンクの容量が小さいキッチンカーの場合は、キッチンカーで提供許可な品目数が制限される場合があります。飲食店営業許可で1品目しか販売が認められていないと、「焼きそば+ビール」で提供したいと思っても「焼きそば」しか販売できないので、結果的にお酒を販売できません。
利益率を上げるために「アルコール提供もしたい!」という人は、この点も考慮してキッチンカーの車種を選びましょう。
4.出店場所がお酒の販売を認めている
キッチンカーは出店場所を管理する人の許可を得て営業します。この出店場所によりメニューの制限がある場合があります。たとえばフェスなどのイベントへの出店では、お酒(アルコール)は売り上げの花形商品のため、販売制限を受けることがあります。
大分県でもお酒(アルコール)販売が可能です
インターネット上では「大分県のみキッチンカーでお酒を販売できない」という情報を見かけます。実際に大分県別府市にある東部保健所に電話で確認したところ、「大分県内でもキッチンカーでのお酒の販売は可能」という回答をいただきました(2023年6月14日確認)。インターネット上の誤った(古い)情報をうのみにしないよう注意してください。
キッチンカーで缶・瓶に入ったお酒(アルコール)は販売できない

飲食店営業許可を取得することで、キッチンカーでも開栓状態のお酒(アルコール)を販売できることがわかりました。ではキッチンカーで移動販売を目的として、国税庁の免許を取得したら未開栓の酒類の販売はできるのでしょうか?
答えは「できません」。
酒税法(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=328AC0000000006#105)の第9条が、酒類販売業に関する条文に当たりまして、国税庁による法令解釈で次のように示されています。
16 酒類の移動販売の取扱い
一定の販売場を設けず、自己の住所等を根拠として酒類を携行し、又は運搬車、舟等に積載して随時随所において注文を受け、酒類を引き渡し、又は酒類の販売代金を受領する等の方法により酒類の小売を行ういわゆる酒類の移動販売に対する酒類小売業免許については、当分の間付与等しない。
引用 酒類の販売業免許(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sake/2-06.htm)
つまり「自動車はお酒の販売場としては認めていないので酒類販売業免許は与えません」ということになります。ここまでをご説明してキッチンカーでもアルコールが販売できるとわかると驚かれる方も多いのですが、アルコールを販売できないと思っていた理由を聞いてみると、この国税庁の法令解釈を人から聞いた、という方がほとんどです。
キッチンカーでのお酒(アルコール)販売に関するよくある質問

Q1:カップに注がなくてもよいの?
A1:カップに注がなくても販売の問題はありません。缶ビールであればプシュ!っと抜栓した状態であれば販売はできます。しかし抜栓した缶ビールの販売では消費者目線からも売価を高く設定しづらいため、カップに注いだ販売をされる方も多いようです。
Q2:カクテルやソーダ割りを作って販売できる?
A2:はい、カクテルやソーダ割りを作って販売することも可能です。ただし、カクテルに苺やグレープフルーツのような生フルーツやミントのような生の葉っぱを使ったものは販売できない都道府県がありますので事前に保健所に確認をおこなってください。
Q3:アルコール販売のときに氷は使えますか?
A3:はい、氷も使えます。ただし氷の使用については保健所のガイドラインで別のルールがありまして、キッチンカーの給水タンクの水を使って凍らせた氷は飲用には用いることができません。アルコール・ソフトドリンクを問わず、氷を使いたい場合は、製氷業者から仕入れた氷や、スーパーなどで売っている袋詰のロックアイスを用いて提供してください。
Q4:価格はいくらで販売してもかまわないのですか?
A4:はい、いくらで販売しても大丈夫です。メインのフードとアルコールのセット販売で客単価を上げることをおすすめします。
Q5:おすすめのアルコールはありますか?
A5:基本的に、フードもドリンクも出店場所や時間帯に合ったものが売れる傾向にあります。ドリンクはコンビニや自販機と価格比較されてしまうこともあります。フードトラックカンパニーのおすすめのアルコールの一つに、クラフトビールがあります。
クラフトビールは商品に特別感や人気があるだけでなく、種類も豊富で、コンビニや自販機で売っていないため比較されにくい商品です。フードトラックカンパニーでキッチンカーをご購入いただいた方は、ビールメーカーのキリン様のクラフトビール用のビールサーバーを無償で借りることができます。初期費用を抑えてアルコールを販売したい方におすすめです。
まとめ
キッチンカーの営業許可が取得できていれば、コップなどに注いでビール・ハイボール・ワインとさまざまな種類のお酒(アルコール)を販売できます。もちろんビールサーバーで注いだ生ビールもイベントでの販売も可能です。缶・瓶に入ったアルコール類を販売するわけではないので、酒類販売業免許は不要です。ただし、キッチンカーでは酒類販売業免許を取得できません。
お酒(アルコール)を含むドリンク類はもちろん、キッチンカー運営全体について学べるのは株式会社フードトラックカンパニーが開催しているキッチンカー開業セミナーです。地方都市を含む全国各地のセミナー会場とオンラインの両方で視聴できるので、どなたでも気軽に参加できます。キッチンカーの開業に興味があるなら、ぜひ参加して多くのことを学んでください!